コンパウンド 開発ストーリー
ヨクとユメは叶わないから在る

日常的に誰にでも使える金属研磨剤、ただ布につけて磨くだけで輝きと艶がでる研磨剤は無いのだろうか?10年以上前から、Morita Polish Artists(以降、森田PA)は探し続けていた。
自分が磨きあげたパーツをお客さんに渡すとき、「この研磨剤でメンテナンスするといいですよ!」と自信を持って薦められるものがない。特にアルミパーツは経年劣化により表面が酸化し徐々に艶を失っていくため、元々の艶を復活させるための良い、お勧めできる研磨剤がなかった。
国内メーカーの一般向け金属研磨剤はほとんどがペースト状または固形のものだ。使っている人も多いのでわかると思うが、きちんと研磨できなかったり(キレが無い)、逆に削れ過ぎてしまったり、何種類か使い分けしなければいけなかったり、なかなか思うような輝きと艶を得られない。
海外から輸入されているさらっとした液体タイプの金属研磨剤もあり、それを薦めていたこともあるが、結局、満足できる艶を出せるものではなかった。
研磨剤には相反する2つの性能がある。削る(表面をよく削ること)と磨く(鏡面に磨きあげること)だ。この2つの性能を一つの研磨剤に併せ持つことは難しい。例えば、紙やすりには必ず番手と言われる目の粗さがあって、工程に応じて目の粗いもの(番手の小さいもの)から目の細かいもの(番手の大きいもの)に使い分けていく。金属の表面を鏡面に仕上げる場合、面を整えるための『削り』と、その削り目(やすり目)を消して仕上げる『磨き』という工程の段階を踏まなければならない。
『削り』は、磨きたい金属の表面の状態に応じて、粗いサンドペーパーなどで削りながら面を整えていく。例えば、120番のサンドペーパーでスタートした場合、120→150→180→240→320→400→600→800→1000…と番手を上げていくのだが、大切なのは前の番手のペーパー目(やすり目)を次の番手で確実に消すことだ。 アルミの場合、600番が終了した段階でぼんやりと周りの物が映りこむようになる。
研磨のプロは、最低でも3種類の研磨剤を段階によって使い分けているが、限りなく鏡面に仕上げたい場合は、10種類以上の研磨剤を使い分けることもある。良く切れる(切削能力の高い)研磨剤ほど仕事は速いが、艶に深みが出ない。これは研磨剤の粒子が粗いのが原因である。逆に艶に深みの出る研磨剤は切れない。(切削能力が低い)これは研磨剤の粒子が細かすぎるためである。
一般の人が金属磨きを行う場合、ひとつの研磨剤で『良く切れて』『良く光る』、ワイドレンジな(欲ばりな)研磨剤が理想なのだ。 金属を磨くということは決して容易ではない。だからこそ、少しでも作業性の良いものが欲しかった。
プロとプロの出会い
5年前、ひとつの出会いがあった。某国内メーカーの営業マンだ。彼と話をしていると、一つの意外な事実が見えてくる。“メーカーは、研磨のプロと研磨剤を共同開発したことがあまり無かった”のだ。森田PAはこれに驚いた。
もちろん、某国内メーカーはプロが使って納得の研磨剤を作っているし、一般向けにも広く販売され一定の評価を得ている。だが、もっと高みがあるのではないか。一般の人(ここでいう一般の人とは、専用の研磨機械を使わず、趣味の範囲で研磨剤を使用している人)が磨いても、もっと深い艶の出る研磨剤、もっと手軽に使える研磨剤、もっと速く磨ける研磨剤、そんな研磨剤はつくれないのか。
出会いから1年後、森田PAの方から新しい研磨剤の開発を持ちかけた。今まで森田PAが使っていて最も評価の高かった研磨剤、それを超える研磨剤の開発を。
そこから森田PAと某国内メーカーとの二人三脚の開発が始まった。一つの道標はあった。固形状の研磨剤は使い分けが難しい。クリーム状の研磨剤はキレが悪い。サラサラ液状の研磨剤(輸入品)だとある程度満足の行く艶を出せる。創り上げるにはサラサラ液状タイプの研磨剤を突き詰めていけばいいのではないか。
それから、試作品を試す日々が続いた。最終的にはパーツも磨いてみるが、なかなか満足するものができない。キレがよく、ある程度の輝きまでは出るが、どうしても“艶”に満足できない。もちろん、メーカーの開発チームがこれだ!と送り出してきているものだから、普通に輝きの出るいい研磨剤ではある。
でもちがう。今あるものと同じものでは意味が無い。これしかないからなぁ、と使っているものと同じものでは意味が無い。
ある日、担当者が「これがダメならもう他にありません。でもこれなら!」といいながら一本の試作品を持ってきた。また同じだろうなぁと半ば諦めながら、磨いてみた。
お?、これはイケる。
これまでとは艶が違う。キレもいい。アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、、、 いろいろな素材で試してみた。実際の磨き仕事にもしばらく使ってみた。周りの人にも使ってみてもらった。評価は上々だった。これなら自信を持って勧められる。
サンプルAがようやく仕上がった。
もちろん、某国内メーカーはプロが使って納得の研磨剤を作っているし、一般向けにも広く販売され一定の評価を得ている。だが、もっと高みがあるのではないか。一般の人(ここでいう一般の人とは、専用の研磨機械を使わず、趣味の範囲で研磨剤を使用している人)が磨いても、もっと深い艶の出る研磨剤、もっと手軽に使える研磨剤、もっと速く磨ける研磨剤、そんな研磨剤はつくれないのか。
出会いから1年後、森田PAの方から新しい研磨剤の開発を持ちかけた。今まで森田PAが使っていて最も評価の高かった研磨剤、それを超える研磨剤の開発を。
そこから森田PAと某国内メーカーとの二人三脚の開発が始まった。一つの道標はあった。固形状の研磨剤は使い分けが難しい。クリーム状の研磨剤はキレが悪い。サラサラ液状の研磨剤(輸入品)だとある程度満足の行く艶を出せる。創り上げるにはサラサラ液状タイプの研磨剤を突き詰めていけばいいのではないか。
それから、試作品を試す日々が続いた。最終的にはパーツも磨いてみるが、なかなか満足するものができない。キレがよく、ある程度の輝きまでは出るが、どうしても“艶”に満足できない。もちろん、メーカーの開発チームがこれだ!と送り出してきているものだから、普通に輝きの出るいい研磨剤ではある。
でもちがう。今あるものと同じものでは意味が無い。これしかないからなぁ、と使っているものと同じものでは意味が無い。
ある日、担当者が「これがダメならもう他にありません。でもこれなら!」といいながら一本の試作品を持ってきた。また同じだろうなぁと半ば諦めながら、磨いてみた。
お?、これはイケる。
これまでとは艶が違う。キレもいい。アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、、、 いろいろな素材で試してみた。実際の磨き仕事にもしばらく使ってみた。周りの人にも使ってみてもらった。評価は上々だった。これなら自信を持って勧められる。
サンプルAがようやく仕上がった。
テマとツヤに挟まれて
ひとつ、気になることはあった。サンプルAは、溶剤と酸化アルミナがすぐに分離してしまうのだ。商品名「SHAKE MORLEY」の名前の由来にもなったが、都度都度ひたすら振ってから使う必要がある。せっかくいい艶が出たとしても、それ以上に手間のかかる、使いにくい研磨剤になってしまったら、結局使う人が困るのではないか。
混ざりやすくなるよう分散剤も入れてみた。これは失敗。キレが無くなり、艶もイマイチ。研磨剤の材料である酸化アルミナを特注で製造することもメーカーと検討してみた。確かに期待する性能は出るだろうが、とてもとても高くて、研磨剤として売れるものにはならない。これも断念。撹拌用のスプリングを入れてみた。これは少し効果あり。
これ以上やれることはないか。撹拌用のスプリングを改良してみるか。振る手間はかかるが、この艶が出るのならいいか。
森田PAは気になりながらも、これ以上のサンプルAの改良は難しいと考え、発売の準備を進めていった。磨いた時の仕上がりは極上、商品名も決め着々と準備が進んでいく中、どうしてもスッキリしなかった。元々、新しい研磨剤をつくろうと思ったのはなぜか。もっと手軽に使える研磨剤が欲しかったのではないか。ちょっと手にとって、テレビを見ながら磨いていたら艶が出た、という研磨剤が欲しかったのではないか。もっと自信を持って勧められる研磨剤が欲しかったのではないか。
確かに仕上がりはいい。キレもいいから作業も早い。
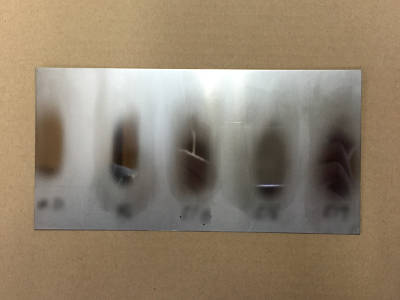
悶々と過ごしていた厳冬の早朝、冷えきったパーツを手に取りながら、森田PAはひとつの決断をした。メーカーの担当者を呼んで頼み込んだ『これまでの開発を白紙に戻して、もう一度ゼロから考えて欲しい。混ざりやすく、仕上がりはサンプルAと変わらないものを』。
当然、メーカーとしては、これ以上のものはないです と断ってくる。これまで数年間かけて開発してきたのだから、それはそうだろう。
だが、このままだと納得できるものにならない。メーカー担当者とこれまでの開発経緯を思い出しながら、一つ一つ、可能性と失敗と成功を共有していく。そして、混ざりにくさが如何に「簡単であること」を妨げているかということも。
「わかりました。これまでの試作品はなかったことにしてください。忘れてください。もう一度、開発をやり直してみましょう!」、担当者が根負けした瞬間だった。
混ざりやすくなるよう分散剤も入れてみた。これは失敗。キレが無くなり、艶もイマイチ。研磨剤の材料である酸化アルミナを特注で製造することもメーカーと検討してみた。確かに期待する性能は出るだろうが、とてもとても高くて、研磨剤として売れるものにはならない。これも断念。撹拌用のスプリングを入れてみた。これは少し効果あり。
これ以上やれることはないか。撹拌用のスプリングを改良してみるか。振る手間はかかるが、この艶が出るのならいいか。
森田PAは気になりながらも、これ以上のサンプルAの改良は難しいと考え、発売の準備を進めていった。磨いた時の仕上がりは極上、商品名も決め着々と準備が進んでいく中、どうしてもスッキリしなかった。元々、新しい研磨剤をつくろうと思ったのはなぜか。もっと手軽に使える研磨剤が欲しかったのではないか。ちょっと手にとって、テレビを見ながら磨いていたら艶が出た、という研磨剤が欲しかったのではないか。もっと自信を持って勧められる研磨剤が欲しかったのではないか。
確かに仕上がりはいい。キレもいいから作業も早い。
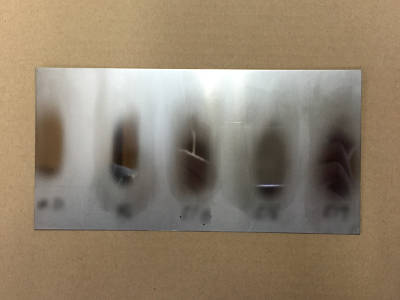
悶々と過ごしていた厳冬の早朝、冷えきったパーツを手に取りながら、森田PAはひとつの決断をした。メーカーの担当者を呼んで頼み込んだ『これまでの開発を白紙に戻して、もう一度ゼロから考えて欲しい。混ざりやすく、仕上がりはサンプルAと変わらないものを』。
当然、メーカーとしては、これ以上のものはないです と断ってくる。これまで数年間かけて開発してきたのだから、それはそうだろう。
だが、このままだと納得できるものにならない。メーカー担当者とこれまでの開発経緯を思い出しながら、一つ一つ、可能性と失敗と成功を共有していく。そして、混ざりにくさが如何に「簡単であること」を妨げているかということも。
「わかりました。これまでの試作品はなかったことにしてください。忘れてください。もう一度、開発をやり直してみましょう!」、担当者が根負けした瞬間だった。
ツヤとキレは同じユメを見るのか
それからしばらく連絡がなかった。
...数週間が経ち、諦めかかって、サンプルAで妥協するのも仕方がないかと思い始めた頃、担当者から連絡が入った。「数週間したらサンプルをお持ちできると思います」
それから2週間後、担当者がサンプルBを持って森田PAを訪れた。サンプルAと区別するために、水色に着色されたサンプルBは明らかに混ざりが良い。これは期待できる。

早速、磨いてみた。キレもいい。サンプルAよりもキレるくらいだ。
そのまま磨いてみる。
??? 艶が出ない、いや、輝きも悪い。 細かい傷も残る。
仕上がりはとても満足できるものではなかった。一番大事なところが犠牲になってしまった。やっぱり無理なのか。実現不可能な課題を押し付けているだけなのだろうか。森田PAは苛立ちを押し殺しながらメーカーに使用感をフィードバックした。
担当者は淡々とフィードバックを受け止めていた。ただ、「もう一週間だけ待ってください。全く違う別サンプルを持っていきます。」とだけ回答があった。
一週間後、担当者がサンプルCを持ってきた。黄色く着色されていることを除いて、見た目はサンプルBと変わらない。混ざりは良い。キレも良い。そのまま磨いていくと、
艶も良い、深みもある!!
これだ!!
5年をかけて開発してきた研磨剤がようやく仕上がった。キレがよく、深い艶が出て、ストレスを感じることなく使い始められる研磨剤が。ひとつ残った疑問は、なぜ今までサンプルCのような研磨剤が出来上がってこなかったのか、ということ。率直に聞いてみたら、「以前までは、森田PAが業務で使っている研磨剤や輸入品の液状研磨剤をベースに考えてきた。今回は、これまでとはまったく違う材料の組み合わせを試している。」(企業秘密もあるのでボカした表現になっています)とのことだった。
その後、いくつかの配合を試し、2015年9月、SHAKE MORLEY(シェイク・モリー)は完成した。
...数週間が経ち、諦めかかって、サンプルAで妥協するのも仕方がないかと思い始めた頃、担当者から連絡が入った。「数週間したらサンプルをお持ちできると思います」
それから2週間後、担当者がサンプルBを持って森田PAを訪れた。サンプルAと区別するために、水色に着色されたサンプルBは明らかに混ざりが良い。これは期待できる。

早速、磨いてみた。キレもいい。サンプルAよりもキレるくらいだ。
そのまま磨いてみる。
??? 艶が出ない、いや、輝きも悪い。 細かい傷も残る。
仕上がりはとても満足できるものではなかった。一番大事なところが犠牲になってしまった。やっぱり無理なのか。実現不可能な課題を押し付けているだけなのだろうか。森田PAは苛立ちを押し殺しながらメーカーに使用感をフィードバックした。
担当者は淡々とフィードバックを受け止めていた。ただ、「もう一週間だけ待ってください。全く違う別サンプルを持っていきます。」とだけ回答があった。
一週間後、担当者がサンプルCを持ってきた。黄色く着色されていることを除いて、見た目はサンプルBと変わらない。混ざりは良い。キレも良い。そのまま磨いていくと、
艶も良い、深みもある!!
これだ!!
5年をかけて開発してきた研磨剤がようやく仕上がった。キレがよく、深い艶が出て、ストレスを感じることなく使い始められる研磨剤が。ひとつ残った疑問は、なぜ今までサンプルCのような研磨剤が出来上がってこなかったのか、ということ。率直に聞いてみたら、「以前までは、森田PAが業務で使っている研磨剤や輸入品の液状研磨剤をベースに考えてきた。今回は、これまでとはまったく違う材料の組み合わせを試している。」(企業秘密もあるのでボカした表現になっています)とのことだった。
その後、いくつかの配合を試し、2015年9月、SHAKE MORLEY(シェイク・モリー)は完成した。
Morita Polish Artists から
クラシックカーの文化が日常に溶け込んでいる欧米に比べると、日本のクラシックカーやバイクの文化はまだまだ成熟の余地があるのかもしれません。欧米の、特に米国のコンセプトやデザイン、パーツ自体を輸入することが多いのも現実かと思います。ただ、そのような状況にあっても、世界に向けて、日本発のもの、Awesome!(これはすげぇ!)と言われるもの、を発信していきたいと思っています。まずは日本国内で認められ、そして世界に向けて発信できるように、今後も開発、改良を続けていきますので、皆様からの忌憚なきフィードバックを期待いたします。
また、数値や言葉で表現できない開発に根気よく付き合っていただいた、そしてこれからも付き合っていただけるであろうメーカーおよびその担当者に感謝いたします。
また、数値や言葉で表現できない開発に根気よく付き合っていただいた、そしてこれからも付き合っていただけるであろうメーカーおよびその担当者に感謝いたします。


